≪秋の銘ー月・月見≫
・玉兎(ぎょくと、たまうさぎ)
月の異称。
・月の桂、桂月(つきのかつら、けいげつ)
月の異称。桂月は桂花キンモクセイの花が咲く月という意味がある。
・嫦娥(こうが、じょうが)
月の異称。中国古代の伝説上の人物。
・有明、有明の月、残月(ありあけ、ざんげつ)
月がまだ空にあり夜が明けてくるころのことをいう。また朝の空に月が淡くかかっている状態も同じく。月の運行を基準にする旧暦十六日以降の月は、月の出が遅くなり朝まで月が残ることこから。
・夕月夜(ゆうづきよ、ゆうづくよ)
夕方だけに月のある夜をいう。
・夜半の月(よわのつき、よはんのつき)
夜半は夜中のこと。秋の夜更けにでている月をいう。
・月見、月の宴→月の友、月の客
旧暦八月十五日「仲秋の名月」、九月十三日「後(のち)の月」に月を鑑賞すること。月見を共にする人を月の客、月の友という。
・十三夜、後の月(じゅうさんや)、豆名月、栗名月
旧暦九月十三日の夜を指す。団子に枝豆や栗を添えて供えることから豆名月、栗名月とも呼ばれる。
・十五夜、仲秋の名月、望月、芋名月(じゅうごや、ちゅうしゅうのめいげつ、もちづき)
旧暦八月十五日の月をさす。ススキを立て小芋・里芋と団子を供えることから芋めいげつとも。
・無月、雨月(むげつ、うげつ)
空が曇り仲秋の名月が見られないこと。雨月は雨のため月が見られないこと。雨月は五月の異称でもある。
・十六夜(いざよい)
仲秋の名月の翌日をいう。「いざよい」にはためらう・躊躇するの意「いざよう」の名詞形、十五夜より少し遅れてためらいがちに出ることから名付けられた。
・立待月、居待月、臥待月、更待月(たちまちづき、いまちづき、ふせまちづき、ふけまちづき)
十五夜の翌々日十七日の月は十六夜の月より三十分あまり遅く出ることから「立って待つ」意味でそう呼ばれる。その後次第に月の出は遅くなることから十八日の月を居待月、十九日の月を臥待月、二十日の月は夜も更けた午後十時ころに出るので更待月と呼ばれる。
・二十三夜、弓張月(にじゅうさんや、ゆみはりづき)
真夜中に東の空より昇る旧暦二十三日の月は左半分が輝いて見える下弦の月となり、右半分が見える七日の上弦の月とともに弓張月と呼ばれる。
・月待(つきまち)
多くの人が夜に集まり、飲食をした後に月を拝み、月が昇るのを待つ風習。
・庵の月(いおりのつき)
人里離れた静かな侘び住まいに座って眺める月はひとしおに心にしみる様。
・盆の月(ぼんのつき)
盂蘭盆会(うらぼんえ)に入って初めての満月をいう。旧暦七月十五日。
次回は、茶の湯の銘ー季節のことば「秋ー暮らし」
※参考文献「茶の湯の銘 季節のことば(淡交社)」

当店では新旧・書付ものからお稽古もの問わず
お茶道具であればきちんと拝見、買取りさせていただきます。


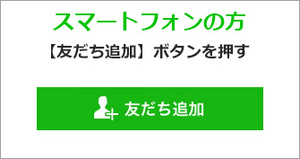

コメント